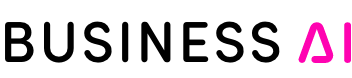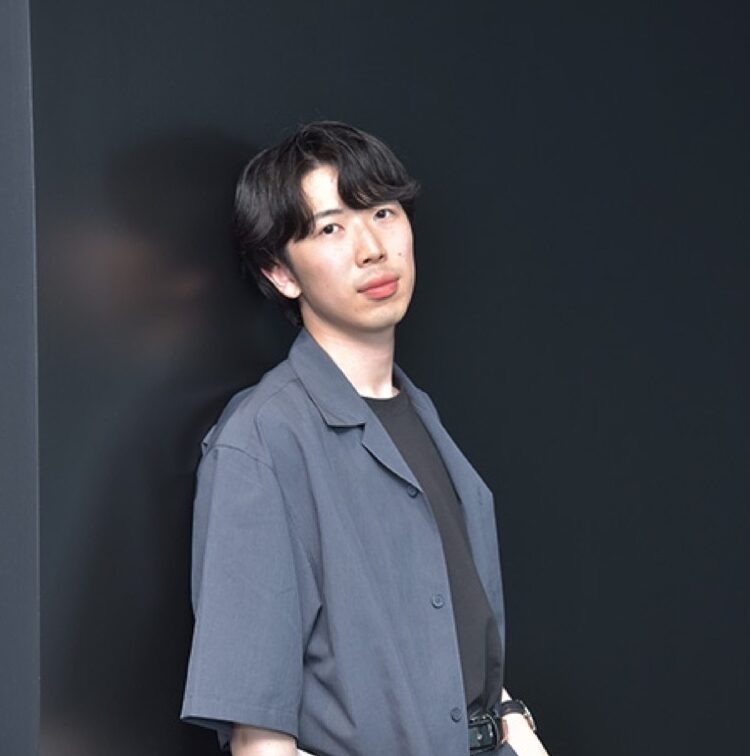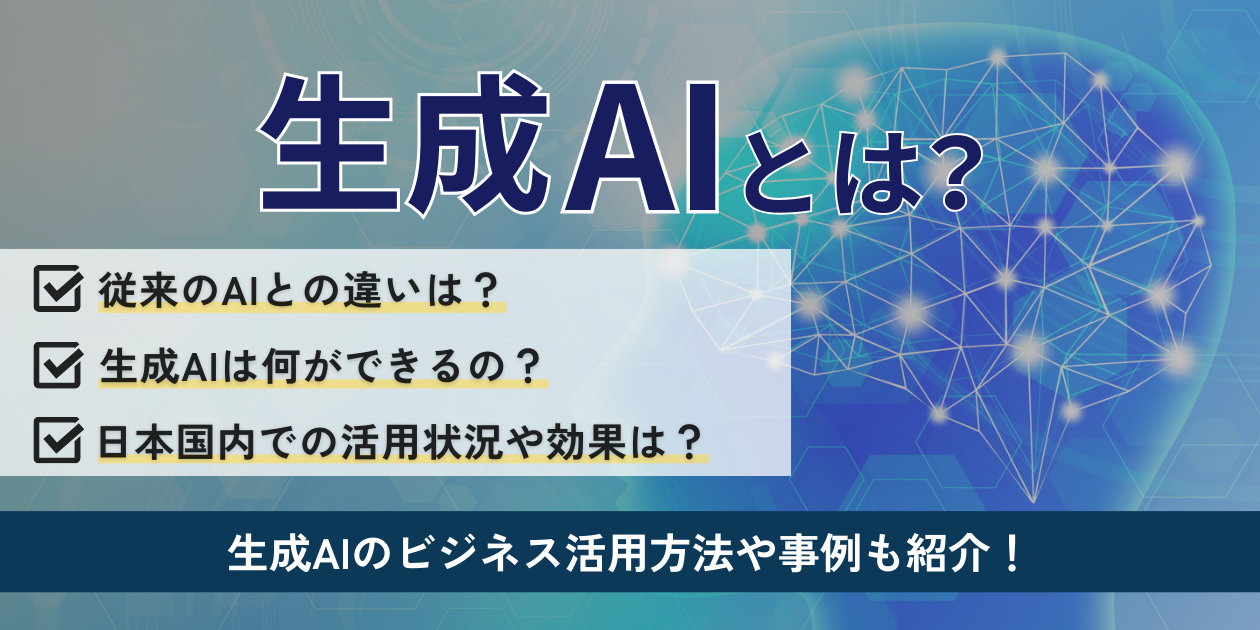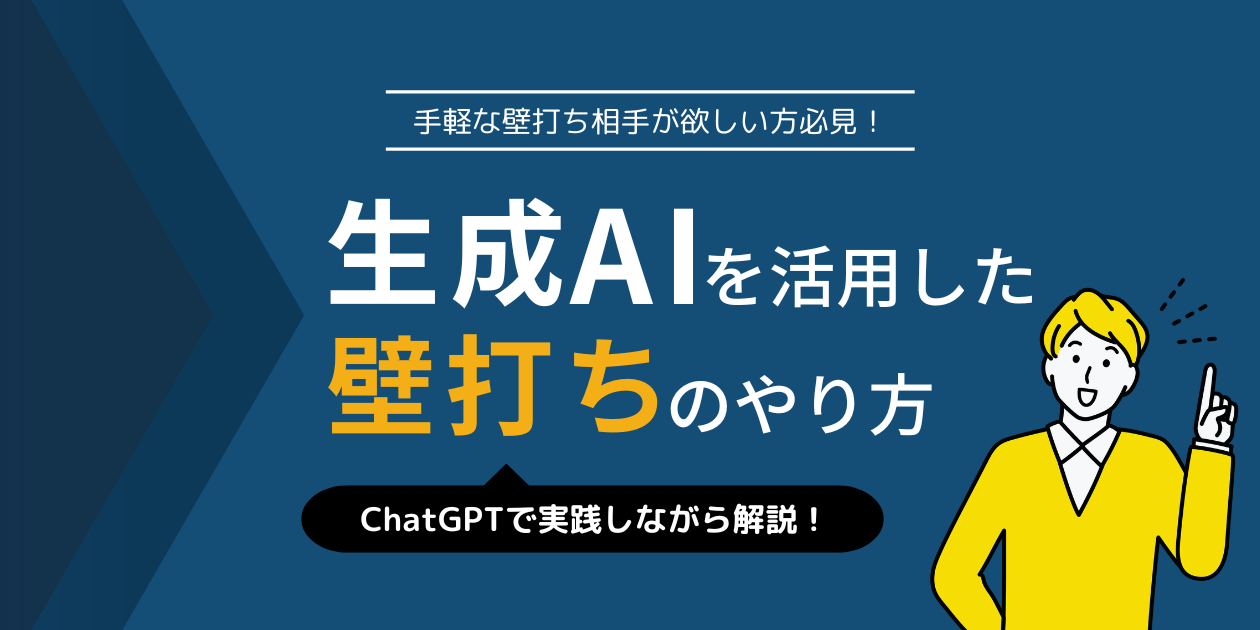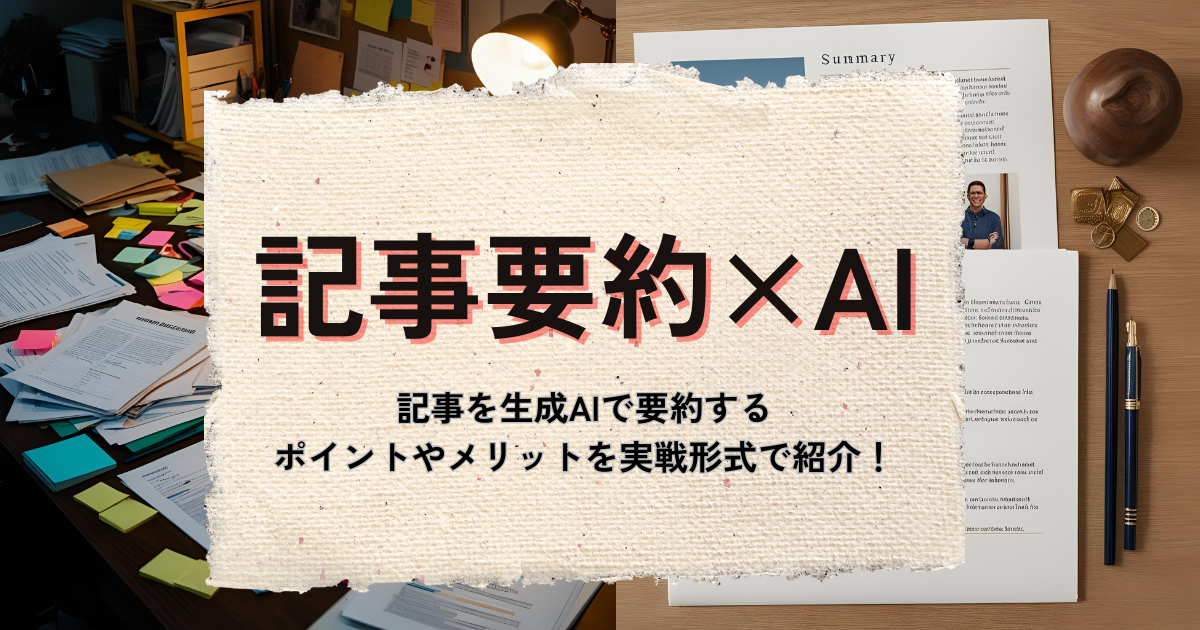
記事要約に生成AIを用いるメリットは?良い要約を作成するための工夫などを実践形式で紹介!
株式会社C And 代表取締役
ネット記事やニュースは、情報収集する上でなくてはならないものになりつつあります。そんなネット記事やニュースによる情報収集は、生成AIを用いて効率化することができます。
今回は生成AIを用いて記事要約を行い、情報収集を効率化するためのポイントや工夫の仕方について実践を交えながら紹介します。
目次
記事要約を生成AIで行うメリット
生成AIを用いて記事の要約を行うと、以下のようなメリットを得ることができます。
記事要約を生成AIで行うメリット
- 情報収集を効率化できる
- 記事の内容が把握しやすくなる
- 情報収集内容のアーカイブが作成できる
情報収集を効率化できる
生成AIを用いて記事を要約することで、記事を読まなくても内容の要点を短時間で把握することができるため、情報収集を圧倒的に効率化できます。
また生成された内容が要約されすぎていると感じた際には、特定の部分のみをより詳しく生成してもらうといったことも可能です。そのため、欲しい情報の強度に合わせた情報収集もできます。
記事の内容が把握しやすくなる
情報収集するにあたり、記事をしっかり全部読みたいという方もいらっしゃるでしょう。
そのような方にも、生成AIによる記事要約はおすすめできます。記事の要点を記事を読む前に確認することで、記事の概要を読む前に把握することができます。
これにより、
- 記事を読むことで自分の得たい情報が得られるのかの判断
- 記事概要がわかっているため記事への理解度が上がり読み返し等が少なくなる
といったメリットを得ることができます。
効率よく情報収集内容のアーカイブが作成できる
記事を読んで今後もその記事の内容が役に立ちそうだと思った際にも、生成AIによる記事要約が活用できます。
生成AIが短時間で要約を作ってくれるため、その要約に足りない内容をつけ足したり逆に不要な内容を削除することで、1から作るよりも圧倒的に早くアーカイブが作成できます。
記事要約を生成AIで実演
では実際に、生成AIを用いて記事の要約を実践してみたいと思います。
今回は、現在最も広く使われているツールの一つである「ChatGPT」を用いて命令内容(プロンプト)の作り方、実践の順で紹介します。
命令内容(プロンプト)の作り方
記事要約のためのプロンプトを作る際には、以下のように「命令内容」「要件」「記事の内容」「出力例」を明記するとすると良いでしょう。
あなたは文章要約のプロです。以下に示す記事の要約をします。その際に、以下に示す要件に沿って要約を作成してください。
#要件(もしあれば)
“記事を要約してもらうにあたりChatGPTに注意してほしい内容”
#出力例(もしあれば)
“出力してほしい方式の例示”
#記事の内容
“記事の内容をコピーしてペーストする”
命令内容は上記のようにChatGPTに役割を与え、何をしてほしいかを明確に指示しましょう。記事の内容に関しては、要約したい記事の要約したい部分をドラックしてコピー&ペーストし実行することでその内容の要約を生成してくれます。
またこのうち「要件」と「出力例」は、もしまとめ方に具体的なイメージがある際にプロンプトに入れるとイメージしている通りの出力に近づけることができます。
しかし、もしそのようなイメージがない場合は、入れなくても簡単な要約を生成してくれます。要件や出力例の具体的な例は、後ほど行う実践の際に示します。
記事要約の実践
今回は、本メディアが公開している以下の生成AIについての解説記事の内容の要約を行います。ここでは以下の3パターンについて解説します。
今回要約に用いる記事
1.要件や出力例を示さないパターン
まずは、要件や出力例を入れずに要約してもらいます。以下のようにプロンプトを入力し要約してもらいます。
これはプロンプトの一部ですが、この下には記事の内容の続きが入ります。この記事の内容は記事の全文をコピー&ペーストして問題ありません。
このようなプロンプトで要約を実行した場合、以下のような結果を得ることができます。
このように要件や出力例を入れない場合、簡潔な要約が出力されます。
「記事の内容を把握しやすくする目的」の場合は、この程度でも十分でしょう。しかし、情報収集を目的とする場合もっと詳しい内容が必要になると思います。そこで有効なのが次に紹介する「要件」の追加です。
2.上記のプロンプトに要件を追加したパターン
ここでは1の命令と記事内容のみのプロンプトに、要件を追加した場合の要約結果を示します。
まず以下のようなプロンプトを用意しました。
このプロンプトは一部であり、この下には記事の内容の続きが入ります。
このようなプロンプトで記事の要約を実行した場合、以下のように要約されます。
この要約はパターン1と比較しても、指示した要件に沿った要約を行ってくれていることがわかります。
このように、要件を指示することで自分の求める要約内容に近づけることができます。そのため、情報収集をどの程度しっかり行いたいのか、その記事からどのような情報を収集したいのかによってこの要件を変えることで、自分の目的にあった要約の生成が可能になります。
3.出力例まで指定するパターン
出力例を指定するメリットとして、自分のイメージした構造で出力されることがあります。そのため、これはアーカイブの作成の際などに特に有効な手段と言えるでしょう。
今回は1で紹介したプロンプトに、「表形式でまとめてください」と出力例を追加して、要約を実行しました。
すると、以下のような要約が出力されます。
今回は表形式と指定するだけで、このように表にまとめて出力してくれます。
また表形式以外でも、他に明確なイメージがある場合は、その旨を要件や出力例に加えることで自分のイメージする出力に近づけることができます。
記事要約の際のプロンプトの工夫
上記でプロンプトの作成の仕方について簡単に解説しました。
プロンプトをさらに良いものにするためには、以下のようなポイントに注意すると良いでしょう。
記事要約の際のプロンプトの工夫
- 記事要約の目的を明確にする
- 複数の記事を同時に要約する
- 条件を追加して希望に沿う回答を得る
記事要約の目的を明確にする
自分のイメージする形の要約を得るためには、要件を指定することが重要であると解説しました。
この要件を指定するにあたって、記事を要約する目的がはっきりしていると、満足のいく出力結果を得るためのプロンプトを作成しやすくなります。
複数の記事を同時に要約する
さらに効率よく情報収集を進めたい場合に、複数の記事を同時にプロンプトに組み込み、それらの要約を行うことが有効です。
やり方は非常に簡単で、以下の例のように「#記事2」や「#記事3」をプロンプト中に追加することで可能になります。
この場合は、「それぞれの記事の共通点についてまとめて」や「それぞれの記事の異なる部分についてまとめて」のように自分の目的に沿った要件の指定が特に重要になります。
複数の記事を同時に要約するプロンプト
あなたは文章要約のプロです。以下に示す記事の要約をします。その際に、以下に示す要件に沿って要約を作成してください。
#要件(もしあれば)
“記事を要約してもらうにあたりChatGPTに注意してほしい内容”
#出力例(もしあれば)
“出力してほしい方式の例示”
#記事の内容
##記事1
“1つ目の記事の内容をコピーしてペーストする”
##記事2
“2つ目の記事の内容をコピーしてペーストする”
##記事3
“3つ目の記事の内容をコピーしてペーストする”
条件を追加して希望に沿う回答を得る
こちらはプロンプトの工夫とは異なり生成AI使用のコツになりますが、もし出力後に要件や要望を追加したい場合などにプロンプトを作り直すのではなく、追加でその要件を指示することでその要件を反映させたものを出力してくれます。
例えば、「もっと詳しい内容にして」や「要件に○○を追加した要約を作成して」のように指示することでこれが可能になります。
記事要約におすすめの生成AIツールの紹介
近年多くの生成AIが出てきていますが、実際どのツールを使ったらいいか迷う方も多いと思います。
結論からいうと、以下のような対話型生成AIのうちすでに使用されているものや最も使いやすいものを用いるのがいいと思います。
ここでは、おすすめの対話型生成AIの他と比較した際の強みなどについて解説します
ChatGPT
ChatGPTは、Open AI社が提供する対話型生成AIです。このツールはテキスト生成を強みとしています。そのため、文章生成の自然さや文脈理解に特に優位性があります。
またChatGPTはユーザーが多いため、使い方や活用術についての情報が多くあるのが特徴的です。
無料でも使用できますが、無料版で物足りなくなった際には、有料プランを利用することで、非常に高性能なモデルの使用も可能になります。このようにChatGPTは、初めて使う方から生成AIをある程度使いこなせる方まで幅広くおすすめできるツールです。
Gemini
Geminiは、Googleが提供する対話型生成AIです。このツールは、Google Workspaceへの情報のエクスポートもできます。
そのためGoogle Workspaceを普段使用している方は、情報収集しながらその内容をGoogle Workspaceでまとめるといったこともできるため、一度試しに使ってみると良いかもしれません。
Claude
Claudeは、Anthropic社によって開発された対話型生成AIです。Cloudeは、コード生成やプロンプトの図式化などを得意としています。
また、Cloudeには「Artifacts」機能があり、これを用いると生成したドキュメントやコード、図表をチャット履歴とは別に保存できます。
そのため、要約内容をわざわざエクスポートしたくないが残しておきたい方には、非常に使いやすいツールでしょう。
Copilot
Copilotは、Microsoft社がビジネス向けに設計した生成AIツールです。
Microsoft社が提供するサービスのため、Microsoft 365と統合されており、ChatGPTのようなチャット型のAIを利用することができます。さらに、ChatGPT Microsoft 365 Copilotを導入することで、WordやExcel、Powerpoint等にAIを導入することができます。
そのため、日常的なタスクにMicrosoft 365を用いる方はCopilotを用いることで、情報収集内容をMicrosoft 365にまとめるといったことができるためおすすめです。
生成AIは使い方次第で得られる効果が変わる!
今回は、生成AIを用いた記事要約を紹介しました。生成AIは、プロンプトの工夫をすることや応用例をたくさん知ることで、活用の幅が広がったり、出力内容のコントロールが可能になります。
本メディア「Business AI」では、他にも業務効率化のための活用方法を紹介しています。
他の事例も確認し、AIリテラシーを高めることで生成AIから得られる効果を大きくしていきましょう。
他の生成AI活用例に関する記事はこちら
他の生成AI活用例に関する記事はこちら
木俣太地
また、前職の株式会社MIXIで培ったブランドプロモーションスキルを活かし、話題化戦略を意識した制作した生成AI活用のアニメCMは、Xにて680万インプレッションを記録。幅広い形で生成AIを活用して、企業の課題解決に貢献。